
エレファント(2003)
監督 ガス・ヴァン・サント
出演 ジョン・ロビンソン

1999年、コロラド州ジェファーソン郡にあるコロンバイン高校で
世界を震撼させる銃乱射事件がおこった。
本作はこの事件をテーマに、
銃乱射が起こるまでの高校の静かな日常をドキュメンタリータッチで淡々と見せていく。
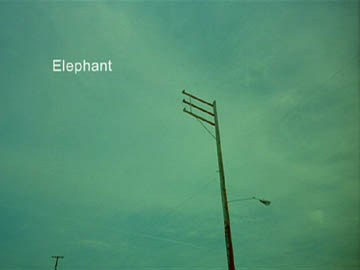 撮影が始まるまで この『エレファント』のきっかけは、 もちろんコロンバイン高校での事件だった。 もともと、ヴァン・サントはテレビ番組用に青少年をテーマにしたものを作ろうとしていた。 そしてハーモニー・コリンが脚本の予定だった。 そんな時におこったコロンバイン高校の事件を テーマにしたテレビ用のドラマを作ろうとした。 しかし、いざプロダクションに持ちかけると、 コロンバイン高校銃乱射事件を具体的に映像化するのは 悲劇の後では刺激が強すぎる、と誰もがNGを出し、 投資することに皆腰が重かった。 そんな中アメリカのテレビ局HBOのヘッドであるコリン・カレンダーと ダイアン・キートンだけがヴァン・サントに手を差し伸べた。 それでも淡々と語るだけの『エレファント』のストーリーテリングに疑問はあったようだ。 ヴァン・サントは、BBCのために作られた アラン・クラークの”Elephant”のようなものなら作れるのでは?と提案があった。 それがこの『エレファント』の起点ともなり、 ヴァン・サントは故郷であるポートランドで撮影に取り掛かった。 どこにでもあるような普通の高校で起きた悲惨な事件を映像化するために、 演技経験のない高校生を募った。そしてセリフが全てアドリブ。 ヴァン・サントはこの”Elephant”は見たことがなかったが、 ハーモニーコリンもこの”Elephant”を絶賛しており、 それなら自分が脚本を書くと言い出した。 しかし、コリンは結局書かなかった、とヴァン・サントは言う。 そこで、『サラ、いつわりの祈り』の原作を書いた小説家JTリロイに脚本を頼む。 プロデューサーのダイアン・キートンはリロイ版を気に入ったが、 当のヴァン・サントはありきたりだと感じ、 結局大まかな流れ以外に脚本や俳優経験者がいない ヴァン・サントの『エレファント』が作られることになった。 撮影 『エレファント』の撮影は、 いつでも変更可能な軽くまとめられた脚本を基にスタートした。 キューブリックの『時計じかけのオレンジ』のように、 8mmレンズを最初用いたが、映像がクリアでないためにうまくいかなかったという。 ヴァン・サントの一番好きなシーンは、 ピアノを弾いているアレックスの後頭部から撮ったシーンだそうだ。 このアレックスが弾く曲はもともと、 シアトルのジャズミュージシャンに作曲を依頼する予定であった。 しかし、ある日、アレックスが撮影の合間にカフェテリアのピアノで ベートーベンの『月光』を弾いていたのを監督が気に入り、そのまま使うことになった。 ガス・ヴァン・サントの映画製作 大学を卒業した後、ロスに移り、 映画界に挑戦しようとハリウッド大通にあるカフェに 一日中座って人間観察をした。 その対象の多くは貧しいながら上を目指している青少年だった。 夢を抱いてロスにやってはきたものの、チャンスに恵まれず、 日々の生活をしていくために、自分を売ったり物乞いをしたりする若者たちに、 ヴァン・サントは魅了されたという。 そして通常ハリウッド映画では路上であくせくしている青少年たちに 焦点を当てることは少なかった、とヴァン・サントは認識していた。 そんな部分に彼は映画のテーマを絞っていく。 しかし、彼が一番目の映画を作るまでにはすでに30代をまわっている、 という早くはないスタートであった。 90年代後半、監督はPinkという小説を書いた。 『マイ・プライベート・アイダホ』で出会った故リバー・フェニックスを主演に、 新たな映画を予定していたが、 フェニックスの死後そのプロジェクトは日の目をみることはなくなった。 このPinkは、ある美しい俳優に執着する監督の話であるが、 その俳優はドラッグの過剰投与で突然死する。 これはリバーフェニックスの死からくるものだ。 ヴァン・サントは以前フェニックスの隣家に住んでおり、 プライベートでも仲が良かった。 そのため、フェニックスの死を心から悼んだ。 いつか、また映画をやろうと約束を交わしたままその約束が果たされることはなかった。 『マイ・プライベート・アイダホ』は高予算の割に興行収入は低かった。 しかし、次の二コール・キッドマン主演の『誘う女』はヒットし、 彼の監督業により広い選択肢が加えられることになった。 また、ラリー・クラークの『キッズ』の エグゼクティブ・プロデューサーを務めるなど、 監督業以外の活動も行っている。 しかし、彼の名が最も知れ渡ったのは、 マット・デイモン、ベン・アフレックが共同で書き上げた 『グッドウィル・ハンティング』であろう。 ヴァン・サントは『グッド・ウィル・ハンティング』や 『小説家を見つけたら』まで、 典型的な「ハリウッド映画産業」というべき完全分業の産業に身を投じてきた。 どうして雇われ監督的なポジションで映画を作ってきたのか、 という質問に対しヴァン・サントはこういう。 自分が作り出す映画に変化をもたらすためにはメインストリートを知る必要があった、と。 自分がこれまでとは違う、自分の映画を作るには、 「温故知新」ともいうべき精神、つまり、現存する方法を知った上で、 それとは違う、斬新でユニークな映画を作り出すことを念頭においていたのだ。 『グッドウィルハンティング』や『小説家をみつけたら』は 彼の初期の映画とは異なるものではあるものの、内容は一貫している。 これらの映画は、数学を通じて、または書くことを通じて、 自分の居場所を求める、悩める若者達に焦点を当てる。 監督がこの若い世代を映し出すのは、 彼らの年が人生で一番バイタリティや活気がある時期だからだという。 その後生み出されるヒッチコックのリメイク『サイコ』は 興行としてはふるわなかったが、ヴァン・サントが長年撮りたかったものだそうだ。 しかし、スタジオに声を掛けてみたが、馬鹿らしい、と門前払い状態だった。 『グッドウィル・ハンティング』の成功によってヴァン・サントが 金を生み出せる監督だと証明されると、 今までの倍となる破格の予算を提示されたのだそうだ。 ヴァン・サントは破滅しかけた人生を送る人々と関わり合うことが多い。 ドラッグストアカウボーイで共著した薬物依存の小説家ウィリアム・バロウズや、 『KIDS』の脚本を担当したハーモニーコリン、 グッドウィルに曲を提供した、自殺したエリオット・スミス。 ヴァン・サントは彼らのワイルドな部分に興味を惹かれるという。 破滅的な面は自分にはないため、だからこそ正反対な面を持つ彼らに惹かれるそうだ。 |